葛飾区金町の歯医者 尾澤歯科医院院長の野村です
平成26年10月12日(日)日本口腔インプラント学会の認定講習会が行われ、講師として参加しました。
認定講習会は専門医受験の登竜門となる講習会。
若手歯科医師のギラギラした視線の中、CGF、採血、静脈確保の講義と実習を行いました。
専門医まで長い道のりですが、この受講生の中から少しでも多くの専門医が生まれる事を願っております。
そして、正しい知識や技術を、多くの患者に役立てていただきたいと思います。
2014年10月13日
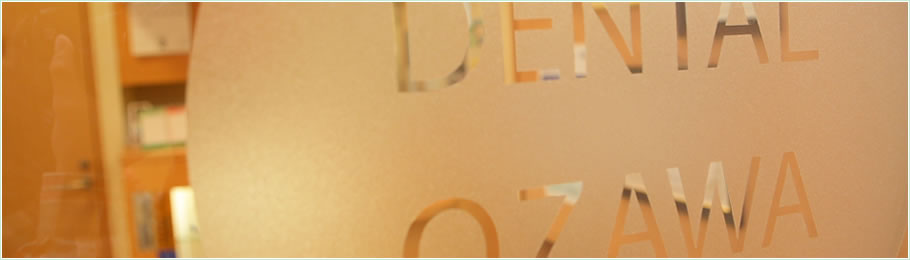
東京都葛飾区金町の歯医者 尾澤歯科医院院長の野村です。
平成26年9月18日 私がCo-director をしているITI Study club Packs Tokyo のミーティングを開催しました。
ITIは世界最大のインプラント研究機関です。
そのITIが主催し、世界各地で勉強会を開催しています。
今回は講師として、神奈川歯科大学の丸尾先生に来ていただき、インプラントの荷重時期に関するレポートをしていただきました。丸尾先生は東京医科歯科大学時代から勉強会を通じて知り合いましたが、ハーバード大学を経て数々の業績を残している先生です。
現在のインプラントは材料の進歩により生体親和性はかなり向上しています。しかし、荷重プロトコルは大きな変化はなく、その科学的根拠も確率してきていることにより、安心感を更に高める事が出来ていると思います。
我々専門医は様々な学術論文を読みます。
しかし、その中でも除外すべき論文、採用すべき論文があります。有効な論文を数多く読む事、また、除外できる知識が必要です。
インターネットからの情報が氾濫する中で、患者さんはこのように除外する知識はありません。
その結果、間違った解釈をしてしまう可能性が多々あるという事です。
分からない事があれば、私達専門医に直接質問をすることが解決の最短距離かと思います。
聞きにくいかも知れませんが、気軽に質問してください。
インターネットに頼るのはお勧め出来ません。
2014年10月5日葛飾区金町の歯医者 尾澤歯科医院院長の野村です。
平成26年9月12日〜14日に東京国際フォーラムにて日本口腔インプラント学会が行われました。
インプラント関連の学会では日本最大規模の学会です。
今年はモーニングセッションにて講演をしました。
口腔底からの出血に対する対処法について講演しました。
AM8:00からのセッションでしたが、会場は立ち見がでて、入りきれないくらいの盛況ぶりでした。
事故がおきないように手術をすることは当然の事ですが、起きてしまったときの対処法について、トレーニングが必要だと考えております。
沢山の歯科医師に興味を持っていただけたら幸いです。
2014年9月21日
葛飾区金町の歯医者 尾澤歯科医院院長の野村です
当院の尾澤文貞理事長の著書が出版されましたので、紹介いたします。
「健康長寿とかみ合わせ」双葉社
尾澤先生は、かみ合わせが原因でおこる体調不良を長年研究しています。
今回は、患者さんの目線での著書ですので、とても分かりやすく書かれています。
かみ合わせ不良による体調不良を診断するのは難しいと思います。
しかし、実際にこのような患者さんは多くいることから、正常なかみ合わせの重要性を強調している本となります。
医者に長年通っているが、原因不明な体調不良が続いている。このような場合は、かみ合わせから引きおこされている場合があるので注意が必要です。
今回の本は、週刊誌(週刊大衆、週刊実話)にも取り上げられました。
2014年8月17日
葛飾区金町の歯医者 尾澤歯科医院院長の野村です。
平成26年7月26、27日の2日間、インプラントスタディーグループ主催のCIDセミナーを開催しました。
今回は裏方と座長としての参加でした。
インプラント本体やその環境の進歩は目覚ましく、全てにおいてクリニック内で取り入れることは出来ませんが、可能な限り患者の利益になることは取り入れています。
このような講演会は情報収集の場になります。海外からの招待講演を含めて、素晴らしい講演会となりました。
ご支援していただいた方々に感謝します。
2014年8月5日
東京都葛飾区金町の歯医者 尾澤歯科医院院長の野村です。
平成26年7月10日(木)葛飾区歯科医師会主催で、障害者歯科研修を都立障害者口腔保健センターにて障害者歯科研修がおこなわれました。
嚥下障害の実習はデモを何度も受けていますが、実際に行うことは初めてでした。
特に、ファイバースコープを用いた嚥下試験をさせていただく機会があり、大変有益なものとなりました。
歯科麻酔科時代に挿管困難症の患者にファイバースコープで気管挿管を行っていましたが、ポジションの違いにより多少戸惑いました。
今後、高齢患者に対して、また違った方向より診断をすることが出来ると思います。
2014年7月10日
葛飾区金町の歯医者 尾澤歯科医院院長の野村です。
先日、日本歯科医師会より、個人研修単位取得数の通知がきました。
これは、学会等に参加すると単位が加算されるようになっており、2年ごとに報告があります。
日本歯科医師会認定の学会が条件のため、単位は少ないかと思いましたが、
私は133単位。全国平均が46のため、平均の約3倍という結果となりました。
仕事をしている以上、一生勉強かと思いますので、これからも研修を怠らずにやっていこうと思います。
私が学会等に行っている間、患者様、スタッフには迷惑をかけています。
感謝の気持ちを忘れず、研鑽していきます。
2014年7月9日
葛飾区金町の歯医者 尾澤歯科医院院長の野村です
平成26年6月22日(日) 公益社団法人 日本歯科先端技術研究所の学術講演会に参加しました。
今回は山口県宇部市にて開催されました。
宮崎県開業の松井孝道先生のご講演のなかに、チタンの腐食に関することがありました。
以前よりチタンの腐食については言われてきていましたが、学会で問題視されることはありませんでした。
チタンは比較的安定した金属で、表面に酸化層を形成しさらに安定するといわれています。
しかし、チタンにフッ素や酸性の強いものなどが付着することで腐食(さび)がおきることがわかってきました。
また、歯の表面に付着するプラーク(細菌のかたまり)が出す酸によっても腐食することがわかってきました。
我々が使用するフッ素は、ムシ歯予防に効果があります。
フッ素のほとんどが酸性ですので、酸により腐食するものと考えています。
歯磨材に含まれるフッ素も同様と思った方が良さそうです。
現在使用されているインプラントのほとんどがチタン製です。
当院にてインプラント治療がされている方へのフッ素塗布は中性のフッ素を使用するようにしています。
また、チタンにはワセリンを塗布し、直接塗らないように注意しています。
インプラント治療をした方は、歯磨材もフッ素が入っていないものを使用しましょう。
2014年6月28日
東京都葛飾区金町の歯医者 尾澤歯科医院院長の野村です
平成26年6月14日(土) 日経新聞の記事
作家の文章ですので、文章構成がとても良いため載せました。
歯ぎしりを自覚されているようでマウスピースにて歯ぎしりを緩和させていたようです。
プラスティックの素材ですので、割れることがあります。
割れたら作り直した方がいいでしょう。
個人差がありますが、体重位かそれ以上の力をかけてしまう方がいます。
もちろん寝ている間ですので無意識です。
普通の食事時にそんな力は必要ありません。
当然歯に負担をかけます。
歯の表面にある固いエナメル質が削れてしまい、象牙質が露出してきます。
場合により、歯が割れることもあります。
このような悪習癖を持つ方は、対症療法としてマウスピースを作成して咬合力を緩和させます。
肩こりや高血圧症が治る場合もありますので、全身に影響を及ぼすと言ってもいいでしょう。
自覚がなくても歯が削れていれば分かりますので、歯科医師による検診を受けましょう。
2014年6月14日© OZAWA DENTAL CLINIC